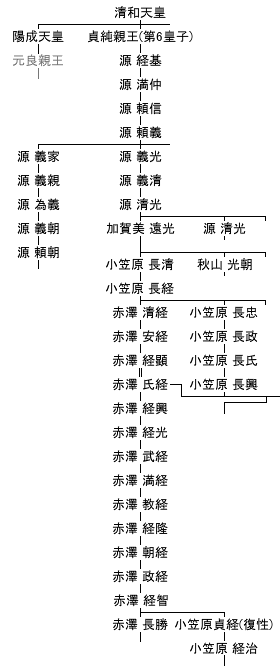| FujiMan Production - プロフィール - |
| 赤沢氏について |
| 新しいページで開いていますので戻るときは閉じてください |
| その後の知見を得たので加筆しました。(2013.09.04) |
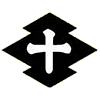 松皮菱に十文字(家紋)
松皮菱に十文字(家紋)赤沢の起源は、清和源氏・小笠原長経(1179-1247)の二男・清経が伊豆守の任を受けて伊豆国赤沢郷を領して赤沢氏を称したことが始まりだといわれています。 清和源氏というのは、56代清和天皇(850-881)の皇子を祖とする姓を与えられ皇族を離れた武家、その中でも源の姓を継いだ氏族のことを指します(*1)。 1192年、鎌倉幕府を開いた源頼朝(1147-1199)もこの氏族のひとりです。赤沢氏の祖先は、遠く皇族から離れた武家ということになります。  塩崎城跡(長野県長野市篠ノ井塩崎) その頃、阿波国(現在の徳島県)にも分かれたようで、居城とした板西城があり、勝瑞城の細川氏とともに阿波守の任に就いたようです。 私の親父は徳島出身だと言っていましたので、こちらの系統のような気がします。 ただ親父からは「源平の戦いで敗れた平家側の落ち武者で、赤沢家は岡山に多い」と聞いていて、 しかもうちの職場に来た取引先の赤沢さん(東北出身)に、苗字が同じなので聞いてみたら、同じような話を聞いたことがあると言われたことがあったので、 まさか源氏(小笠原氏)に謀反を起こした一派なのか? はたまた、情報が錯綜してそう間違って伝わったのか? 疑問に思いながらいろいろ検索してみましたが、 岡山に赤沢の姓が多いのは確かなようですが、平家につながる情報は見つかりませんでした。源平の戦いで敗れた落ち武者が逃れたのが岡山の辺りであったのも確かなようなので、 その情報が交錯して、親父が聞いた言い伝えになったのかも知れません。 その岡山、昔の備中には、小笠原長経の子・長時の子孫が備中守の任を受け三村氏を名乗ったという説があり、その三村氏が同じ備中守の赤沢氏を頼るという話もありました。 この時期についてはよく分からなかったのですが、「母方が赤澤(赤沢)」という方からの情報「関が原の戦い(1600年10月21日)で敗れた豊臣陣営にいた赤沢氏は刀を捨て造船業で財を成す」 (ゲストブックにて頂きました。平謝。)を得て調べましたところ、現在の玉島市にある森本松山城の城主として赤沢左馬祐宗春・五郎四郎宗照(子)・兵庫祐宗栄(孫)、亀崎城の城主として赤沢兵庫頭、畑山城に赤沢久助が入城したようです。 柏島神社は赤沢兵庫頭政定が建立したという記述もありました(*2)。 関が原の戦いで城主赤澤久助が討死したのを機に武士をやめ造船(北前船)で財を成すことになったようですが、この辺りの情報は得られませんでした。 また、関が原の戦いの2年前、京都・北白川の戦い(1558年7月4日)で討ち死にした赤沢長勝の記述があります。この頃、丹波の穴太城の城主として細川氏に仕えていたように思います(*3)。 伊豆、信濃、阿波、丹波、そして岡山と赤沢氏が散らばって、もう何がなんだか分からないようになりますが、鎌倉開幕前後の時代、清和源氏・小笠原氏一族が全国的に勢力を展開していた結果と考えれば 分かりやすいのかなと(これは私の我見ですが)思ったりします(*4)。 このように、歴史家の方にとって、赤沢氏は難解な氏族らしく、起源について、伊豆にいた時期が短いことから不自然ではないかと異を唱える学者もいるとのことです。 ただ、赤沢清経以降、伊豆守を冠する一族があることから、伊豆を起源とするのが一応の通説になっているようです。 ということで、私は武家だ。…しかも皇族出身…ということになりますか(笑)。
参考:(主なもの) 武家家伝_赤澤氏 武家家伝_府中小笠原氏 Wikipedia - 赤沢氏 赤沢氏の系譜 Wikipedia - 小笠原氏 Wikipedia - 清和源氏 信玄を探す旅・塩崎城 Wikipedia - 塩崎城 長野県の城郭・塩崎城 塩崎城 信濃・稲倉城 氏族研究・掲示板 - 小笠原一族の赤沢氏 お城に行こう - 板西城 伊深城 三好氏 玉島柏島 水嶋合戦古戦場趾 岡山県の城跡Wiki 備中赤澤家と玉島古戦記 2013年 9月 4日 加筆
2012年 2月 4日 作成 |
| Copyright(c) 2013 FujiMan Production All Rights Reserved. |