| FujiPro 雑学館 - 雑学 - |
| 万葉時代の男女 |
| トップページ>雑学> 万葉の世界>万葉の男女 |
|
万葉の歌を理解するためには、その時代に立ち返って歌を詠むことが大切だといいます。 万葉集には「恋」の歌がとても多いそうです。現代は通信手段が発達して、想いをすぐに伝えられるから、日常的に「恋の歌」を詠むことはありませんよね。 また、万葉の時代は、男女は夫婦になってからも、相当長い間別居生活が続くそうです。男性は奥さんのところへ通い、夜の明けないうちに帰っていくそうです。 だから夫婦になってからも、恋人同士のような時期が続くわけです。それで女性の歌は、男性が来るのを待つ歌が多く、それも家の中で待つのではなく、 必ず表へ出て戸口で待っているそうです。犬養先生の書には「人間のそこぬけの恋」なんて面白い表現をしています。寒いから…、どうせ来るのは遅いから…、 などとは言わず、みな、表へ出て待っているという理屈抜きの恋みたいな意味なんでしょうか(^^) 磐姫の歌に、次のような歌があります。 『こうやって居続けて、あの方をお待ちしましょう。私の靡く黒髪に夜の霜がついてった構やしない。』と詠んでいます。 万葉集の中には、「降る雪は凍りわたりぬ」と雪の中でも立って待っている。そして「高々に妹が待つらむ」と、少しでも早く会いたいと、背伸びして待っている。 そんな歌が多いそうです。 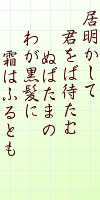 それから、よく似た歌も多いそうです。
それから、よく似た歌も多いそうです。『こうやって夜を明かして、貴方をお待ちしましょう。私の黒髪に、たとえ霜が降ったとしても・・・』 こういうのを「類歌」と言うそうです。流行歌のようにすべての女性に歌われたものと考えられているようです。 磐姫の歌とされているのも、磐姫が飛びぬけて愛情の強い女性だったことから、自然に彼女の歌として語り伝えられたとも考えられています。 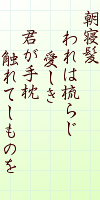 そして、男性が帰ったあとの気持ちを詠った歌も多いそうです。 『朝の寝乱れた髪を櫛梳りませんわ。だって愛しい貴方のお手が触ったのですもの。』 自分の髪には、愛する男性の魂がついているから、その髪をさっと櫛で梳ったりする気持ちにはなれないと詠っています。 |
| <<-TOP <-RETURN | Copyright(c) 2004 FujiMan Production All Rights Reserved |