| FujiMan Production - 日曜大工 - | |
| 基礎編 | 電気の基礎知識(3) |
| トップページ>日曜大工> 電気>電気の基礎知識(3) |
| <-BACK | NEXT-> |
■電気の通り道(電線)
もうひとつ家の配線に使われているのが写真2のものです。被膜が二重になってて中の銅線は太いものがそれぞれ1本です。電化製品のものとは随分違いますね。 電線が太いほどたくさんの電流を流すことができますし、一度配線すれば曲げたり伸ばしたりする必要がありませんから、 屋内配線はこの電線が使われています。 ■抵抗 電気を流すまいとする働きを「抵抗」といいます。学生時代「オームの法則」というのを学習しましたが、そのときに出てきた抵抗のことですが、 ここではその法則の式は出てきませんので安心して下さい。 何が言いたいかといいますと、たとえ電気を流しやすい銅線にも抵抗があるということで、必要以上の電流が流れるとそれ相応の熱が発生するということです。 その熱は自然発火を引き起こすほどで、そのため、それを防止する意味でブレーカーがついているわけです。 ところがブレーカーの許容量にもかかわらず電線が発熱する場合があります。 コンセントプラグを挿したり抜いたり、延長コード(タップ)を使ったり収めたり、そんなとき電線は曲げられたり伸ばされたりしています。 その動作を繰り返している間に、電線被膜の内側では細い銅線が1本ずつ切れてしまいます。するとどうなるんでしょう? 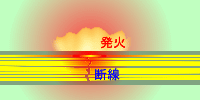 電気は断線して残ったわずかな本数の銅線を通ります。そのわずかな銅線に絶えられる限界を越えた過剰な電流が流れると、発熱を起こします。
発熱すると見かけの抵抗は大きくなり、さらに発熱するという悪循環に陥ります。そしてついには発火することになります。
電気は断線して残ったわずかな本数の銅線を通ります。そのわずかな銅線に絶えられる限界を越えた過剰な電流が流れると、発熱を起こします。
発熱すると見かけの抵抗は大きくなり、さらに発熱するという悪循環に陥ります。そしてついには発火することになります。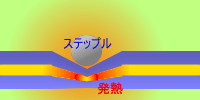 室内配線などで注意したいのが、電線をステップルで固定するときです。ステップルはコの字になった釘のようなものですが、
しっかり固定しようと打ち過ぎると電線被膜だけでなく銅線まで潰れて電気の通り道が狭くなってしまいます。
そうなってしまうと断線して電気の通り道が狭くなったことと同じで、発熱・発火する原因となってしまいます。
室内配線などで注意したいのが、電線をステップルで固定するときです。ステップルはコの字になった釘のようなものですが、
しっかり固定しようと打ち過ぎると電線被膜だけでなく銅線まで潰れて電気の通り道が狭くなってしまいます。
そうなってしまうと断線して電気の通り道が狭くなったことと同じで、発熱・発火する原因となってしまいます。別のコーナーで説明したいと思いますが、そういうときは「配線かくし」を利用します。発熱・発火の防止にもなりますし、 何より見た目もスッキリします。 ■トラッキング現象 これをトラッキング現象といいますが、こうなると発熱、抵抗の増大によってついには発火、火災にまで発展し、住むところがなくなります。 台所をはじめとして、埃の溜まりやすいところ、湿気やすいところ、結露のつきやすいところはとくに要注意です。あわせて覚えておきましょう。 |
| <-前に戻る | つづく-> |
| <<-TOP <-RETUEN | Copyright(c) 2001 FujiMan Production All Rights Reserved |

