| FujiMan Production - 原発は要らない - | |
| 自然エネルギーへシフトしましょう | |
| トップページ>原発は要らない> 自然エネルギーへシフトしましょう |
 12月18日、福島第一原発事故を受けて、国内すべての原発を廃止することを決めたドイツで、総発電量に占める、再生可能エネルギー(太陽光、風力など)の割合が約20%に達して、原発の発電量を上回るとの報道がありました。
原発事故を起こした国が原発を安全だと言って推進して、事故を起こさなかった国が原発は危険だと原発を廃止するという摩訶不思議な状況なのですが、もともと原発に依存している割合が低かったとはいえ、
再生可能エネルギーが原発の電力量を上回るニュースは脱原発を希望する国民にとって朗報となりました。
12月18日、福島第一原発事故を受けて、国内すべての原発を廃止することを決めたドイツで、総発電量に占める、再生可能エネルギー(太陽光、風力など)の割合が約20%に達して、原発の発電量を上回るとの報道がありました。
原発事故を起こした国が原発を安全だと言って推進して、事故を起こさなかった国が原発は危険だと原発を廃止するという摩訶不思議な状況なのですが、もともと原発に依存している割合が低かったとはいえ、
再生可能エネルギーが原発の電力量を上回るニュースは脱原発を希望する国民にとって朗報となりました。原発推進派は原発をなくすなら対案を出せ!と言われますが、原発といえどもその燃料資源はいずれなくなります。これから先の人類のためにも、電力ありき、産業ありき、経済ありき…ではなく、 使えるエネルギーの有効活用を考える機会にならないかと思います。必要なのは原発ではなく電力(エネルギー)のはずです。原発推進論者こそ未来に続くエネルギー論を展開して欲しいと思います。 ただ、そうは言ったものの専門的な詳しいことは分かりません。その辺は専門家にお任せしたいと思います。 2011年12月29日 赤沢富士男
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源は必ず枯渇する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調べたものの中には「石油は枯渇しない」という説もありました(この説は矛盾が指摘され決着したようです)が、これはさておき、新しいエネルギー資源として注目されているメタンハイドレートも含めて、これから100余年先には枯渇してしまうことになります。 つまり人類がずっと利用し続けるエネルギー資源としては、どれも使えないということになると思います。 さらに、ウラン(原子力)に関して言えば、使用しなくなったあとも高レベルの放射性廃棄物を、これまでの人類の歴史と同じくらいの期間管理し続けなければならない点(安全な放射能レベルになるまでには10万年かかると言われています)、とても深刻な問題だと私は思っています。 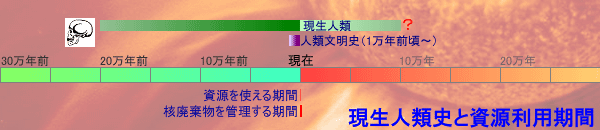 現生人類(新人・ホモサピエンス・Homo sapiens)は約20〜25年前に登場したと言われています。文明が見られるようになって1万年弱ですが、 この時間尺から見ると、いまある石油、石炭や天然ガスなどの化石燃料を、現代人はほんのひと時で使い果たしてしまうように見えます。 それを図示したのが上の図ですが、100年は線にすらなりません。核燃料も資源の利用期間としては同じですが、核のごみ(核レベル放射性廃棄物)の処分後の管理期間である 1,000年ですら線にしかなりません。現生人類、つまり今の人類がこの先何千、何万年と栄えていくのかは分かりませんが、これではあまりに心もとないと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然エネルギーへの転機にしよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 私たちがよく知っている風力発電や太陽光発電、太陽熱発電、地熱発電の他に、水力発電はダムのような大規模な設備ではなく、昔の水車小屋の規模で効率よく発電する新・水力発電や、
身近な発電として振動やテレビやラジオの電波を利用した発電など、微弱でもエネルギーとなるものは利用していこうという研究も進んでいるようです。
首都高速にある五色桜大橋は、そこを走る車両の振動を電気エネルギーに変えて夜間のイルミネーションに利用する実験が行われていることで有名なようです。
私たちがよく知っている風力発電や太陽光発電、太陽熱発電、地熱発電の他に、水力発電はダムのような大規模な設備ではなく、昔の水車小屋の規模で効率よく発電する新・水力発電や、
身近な発電として振動やテレビやラジオの電波を利用した発電など、微弱でもエネルギーとなるものは利用していこうという研究も進んでいるようです。
首都高速にある五色桜大橋は、そこを走る車両の振動を電気エネルギーに変えて夜間のイルミネーションに利用する実験が行われていることで有名なようです。これらの自然エネルギーは、その埋蔵量だけをみれば十分需要分をまかなうことが可能だということで、太陽光や風力などの時間や天候に左右されるものや、 建設コストや維持コストが高いもの、まだ実用化に至っていないものなど、問題点はまだあるようですが、それらをうまく組み合わせることで、100年以上先の未来でも快適なエネルギー利用ができそうな気がします。 とくに家庭照明のような電力は、光源をLEDに変えて、そして身近なエネルギー(振動や風力、太陽光)を利用する、一方、たくさんエネルギーを使う料理や風呂沸かしにはバイオマスを使うようなことが考えられそうです。 電力をたくさん使う会社や企業には、メガソーラーや大規模発電を利用して貰って、もちろん、私たちもエネルギー使いたい放題の生活を見直す必要はあると思いますが、 未来のことを考えて今から少しずつやっていけば、経済だぁ、電力だぁと、たかだか100年そこそこの利権にしがみついている輩より、そちらのほうがよっぽど文化的な人類へ発展できるのではないかと思います。 (マスコミも、もう〜いいかげん取材の方向変えたほうがいいと思うよ。) ※それぞれのエネルギーについての説明は追々増やしていきます。 |
| ※写真はWikipediaのもを使っています |
| トップページ>原発は要らない> 自然エネルギーへシフトしましょう |
| <-RETURN | Copyright(c) 2013 FujiMan Production All Rights Reserved |